故人が亡くなった後、遺品を親族や友人に分け与える「形見分け」は、伝統的には故人が使っていた品物を形見として渡すことが一般的でした。しかし、近年では現金での形見分けも増加傾向にあります。
形見分けは故人の意向や遺族の合意があれば、現金でも問題はありません。本来の形見分けの趣旨とは異なるものの、実際には広くおこなわれています。
本記事では、現金での形見分けに関するマナーや金額の相場について詳しく解説します。記事を参考に、故人の尊厳を大切にしながら、現代に合った形見分けをおこないましょう。
目次
形見分けの本来の意味

形見分けとは故人が生前に大切にしていた品物を、親交のあった友人や家族に贈る伝統的な習慣です。形見分けは義務ではなく、実施するかどうかは遺族の心情や状況によって決められます。
特に形見分けする品物がない場合や保管スペース、処分の負担を考慮して現金を選択するケースが近年増えています。
関連記事「形見分けの進め方を詳しく解説!対象となる品物や時期・マナーや注意点まで」
形見分けを現金にした場合の法的な問題

形見分けとして現金を渡す場合、相続すべき財産から出すことになります。そのため、相続財産の申告の際には、形見分けした現金も含めて正確に申告しなければいけません。
申告漏れがあると、後日税務調査などで指摘される可能性があり、追徴課税や加算税などのペナルティが課される場合もあります。また、形見分けとして現金を受け取った場合、金額が年間110万円を超えると贈与税が発生します。
贈与税の申告は翌年の2月1日〜3月15日までとなっているので、期限内に手続きをおこないましょう。相続について不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
形見分けが現金の場合の4つのマナー

形見分けで現金を渡す際には、以下のマナーに気を付ける必要があります。
- 封筒の書き方
- できるだけ手渡しする
- 渡す時期に決まりはない
- 目上の人には渡さない
相手にも失礼のない形で形見分けをするために、ひとつずつ押さえておきましょう。
封筒の書き方
封筒の表書きの字体は、楷書が基本です。他の字体を使用すると失礼になる場合があります。
字を書くときは筆ペンが理想ですが、用意できない場合は黒のボールペンでも構いません。表書きを書く際は、封筒の上部に余白を取るように書きましょう。仏式の場合、表書きには「遺品」と記すのが一般的です。
封筒は白い無地の物を使用するとよいでしょう。華やかな柄入りの封筒やお祝い用は不適切なので、使用するのは避けてください。
できるだけ手渡しする
形見分けは、できるだけ直接手渡しすることが望ましいです。手渡しすることで故人との思い出話をする機会にもなるでしょう。
直接手渡せない場合は、宅配便を利用する方法もあります。その場合は、必ず一筆添えて形見分けの趣旨を伝える手紙を同封しましょう。
突然荷物が届くと相手を驚かせてしまうため、電話やメールで送付の旨を伝えておくことが大切です。
渡す時期に決まりはない
形見分けを渡す時期は特に決まりはなく、遺族の心の準備が整ったときにおこなうことが一般的です。
仏教の場合、四十九日法要(忌明け)の後におこなわれることが多いとされています。四十九日後は故人の魂が浄土へ旅立つ区切りであり、遺族も心の整理がついている場合が多いためです。
地域や家庭の事情によっては、一周忌を区切りに形見分けをおこなうケースもあります。また、宗教によって形見分けの時期が異なる場合があるため、宗派に合わせておこないましょう。
- 神道:三十日祭・五十日祭後が多い
- キリスト教:三十日目の追悼ミサ後が一般的
故人を偲ぶ気持ちを大切にしながら、それぞれの状況に合わせておこないましょう。
目上の人には渡さない
形見分けを渡す相手は、一般的に故人と親密な関係にあった友人や親族が対象となります。ただし、日本の慣習やマナーとして目上の人(年長者や地位が上の人)に形見分けを渡すことは控えるべきです。
目上の人に形見分けを渡すことは、失礼な行為にあたる可能性があります。
もし故人の意向で目上の人に形見分けを渡す場合は、事前に了承を得ておくと良いでしょう。
形見分けが現金だった場合の金額相場

形見分けの金額に関しては、明確に決められた相場はありません。地域や家族の慣習によっても異なる場合があります。
一般的な傾向としては、数万〜十万円程度の範囲内で設定されることが多いようですが、あくまでも参考となる目安に過ぎません。故人との関係性や遺品の価値によっても変動します。
重要なのは遺族の経済状況や故人の遺志、参加者との関係性などの状況を考慮したうえで、適切な金額を決定することです。
形見分けでもらった現金の使い道
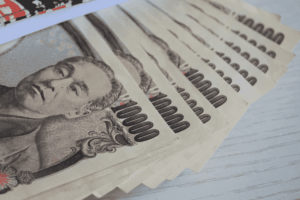
現金で形見分けを受け取った場合、故人を思い出せる品物を購入するのが理想的です。故人が好んでいた食器や小物などを購入すれば、使うたびに思い出しながら偲べます。故人が行きたがっていた場所を訪れる、などでもよいでしょう。
形見分けのお礼は不要で、連絡だけでも良いとされています。受け取りは断れますが、その場合は丁寧にお断りの意思を伝えることが望ましいでしょう。
形見分けでトラブルを避けるコツ5つ

形見分けは感情的な要素が絡むため、トラブルが発生しやすい面もあります。形見分けで起こりがちなトラブルを避けるコツを、5つ紹介します。
- 形見分けの前に遺産分割協議をおこなう
- 文書を残す
- 適切な金額を設定する
- 強要しない
- 専門家に相談する
各ポイントについて詳しく見ていきましょう。
形見分けの前に遺産分割協議をおこなう
形見分けをするには、遺産分割協議により相続人全員の同意を得ることが重要です。遺産分割協議とは、故人が残した財産(不動産、預貯金、有価証券など)を相続人がどのように分けるかを決める話し合いのことです。
全員の意見を尊重し、公平性を保つことがトラブル防止につながります。
相続人が複数いる場合、一部の相続人だけで分配すると他の相続人から不満や異議が出る可能性が高いです。原則として遺産分割協議後に形見分けをおこなうことが望ましいとされており、後のトラブルを未然に防げます。
なお、形見分けを受けると相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄を検討している人は、形見分けを受けるか慎重に考えましょう。
文書を残す
形見分けを現金にする場合、遺産分割協議書に「形見分け用として○○万円を確保する」などと記載しておくことがおすすめです。
相続人全員が形見分けの実施と金額に合意していることが明確になり、後々のトラブルや誤解を効果的に防止できます。また形見分けの対象者と金額の詳細な一覧表を作成し、協議書に添付資料として付けることで、より内容が明確になります。
受取人の氏名や関係性、金額、および必要に応じて形見分けの理由なども記載すると良いでしょう。
適切な金額を設定する
形見分けの金額が高額すぎると贈与税の懸念をされたり、相続の公平性に疑問を持たれたりする可能性があります。一方で、少額すぎると故人との関係性を軽視していると誤解されるなど、後々トラブルにつながることが考えられます。
故人との関係性や受け取る人の状況を考慮して、適切な金額を設定しましょう。同じ立場の人(例えば友人グループ)には同額、異なる立場の人(親族と友人)には異なる金額を設定するなど、関係性に応じた金額に調整することがおすすめです。
不公平感が生じにくくなり、円満な相続や形見分けができます。
強要しない
形見分けの際、もし相手が望まない場合は理由に関係なく無理に勧めないようにしましょう。相手の気持ちを尊重することが大切です。
本来、形見分けは故人の思い出や愛情が込められた品物を大切な人々の間で分け合う意味のある儀式です。そのため、形見の品物をお金に置き換えることを適切ではないと考える人もいます。
相手が形見分けを断った場合、理由に関係なくその決断を尊重し、無理強いしないことが良好な関係を保つうえでも重要です。
専門家に相談する
形見分けで税金が発生したり相続人同士で意見が合わなかったりした場合は、専門家への相談を検討しましょう。税理士や弁護士に相談すれば、以下の問題の解決ができます。
- 相続税や贈与税の申告ミスを防ぎ正しい処理ができる
- 遺産を公平に分配できる
- 家族間のもめごとを減らせる
専門家に早めに相談することで、トラブルを未然に防げます。特に現金が高額だったり相続人が多かったりする場合は、専門家の介入が効果的です。
形見分け現金のまとめ

形見分けは現金でも問題ありませんが、いくつかのマナーに注意する必要があります。
形見分けの封筒は楷書で「遺品」と書き、可能な限り手渡しすることが望ましいです。金額の相場は数万〜十万円程度が多く、関係性や状況に応じて慎重に設定しましょう。金額によっては、相続税や贈与税が関わることもあります。
遺品整理をご検討の際は「遺品整理みらいへ」にお任せください。当社では遺品の整理から処分まで、すべての作業を専任スタッフが丁寧に対応いたします。形見分けが必要な場合や特定の品を残したいなど、お客様のご要望に合わせたサービスを提供しております。ご不明点やご相談は電話・メール・LINEからお気軽にお問い合わせください。







